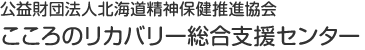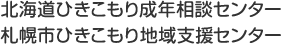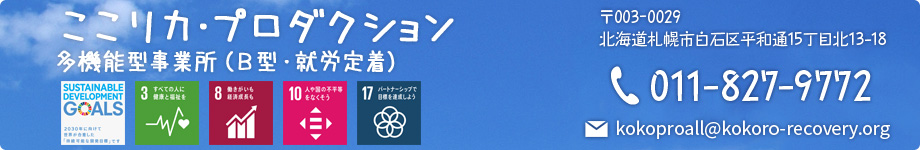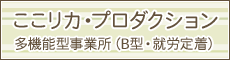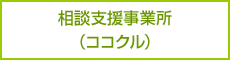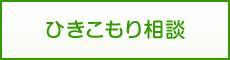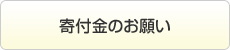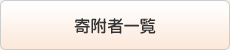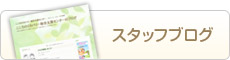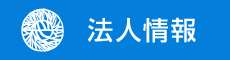理事長ごあいさつ
障碍があるから見える情報がある
公益財団法人北海道精神保健推進協会理事長 阿部幸弘
私達はこのたび、障碍者の手による障碍者と市民のための「メディア事業所」を設立します!…と勢い込んで宣言しましたが、そもそも"メディア"って何でしょうか?よく"媒体"と訳したりもしますが、バイタイ…これまた分かりにくいですね。
私達が考えているメディアとは、人と人とが互いの思いをやり取りする道具のことです。だから、人が集まってワイワイガヤガヤやれる寄り合い場所や、井戸端会議の井戸端さえも、古くからのメディアということになります。(近所に住んでいないと使えませんが…。)
やがて文字が生まれ、石や皮やパピルスに刻まれ、グーテンベルクの印刷革命で大量伝達が可能となり、ついには音や動画までも電送したりディスクに刻める時代になりました。これらの道具はぜ~んぶメディアです。そして今や、地球の裏側に瞬時にメッセージを伝えたり、百年後の未来に映画を届けることも当たり前。そのような、時空を易々と越えられる環境に私達は生きています。
ここまでは、メディアの優れた、そして役に立つ側面のお話しです。
実はメディアには、困った側面もあると思うのです。それは、使われ方の"偏り"です。
たとえば、何かと競争し合う我々人類は、従来の武力による戦争に加えて、お金(経済戦争)や情報による争いをエスカレートさせてきました。IT技術が登場した現在は、まさに情報の流れを牛耳ることがパワー(=権力)の源、そんな時代に行き着いたのです。
このような状況にあって、いつも基本的にマイノリティであらざるを得ない障碍者は、無視されるとまで言わないにしても、なにかと後回しにされる傾向にあるのは事実です。世の中の情報の流れには常に偏りがあるのですが、障碍者は情報弱者にされやすい立場の、代表的なひとつと言えるのではないでしょうか。
けれども、メディアとはそもそも単なる道具でした。だから原則、誰にも開かれて在るはず、と考えてみました。使いこなすには知識や練習が必要でしょう。しかし、障碍を持ってみて分かることや、その立場で生活していて見えてくる体験もあるはずです。考えてみるとこれらは、実は、貴重な情報なのです。
そして、"誰もが障碍者になりうる"という観点から考えた時、障碍者の持っている情報は、本当はすべての人に有益なものになりうるはずです。
ここリカ・プロダクションは、このような発想から計画されました。具体的に何をどう発信していくか、またその技術などは、これから徐々に組み立て身に付けて行きます。精神障碍中心の事業所としてスタートしますので、疲れやすい人でも一緒に働けるよう配慮したいと思います。だからじっくり、ゆっくり歩んで行ければと思っています。
よろしくご支援の程、お願いいたします。
管理者ごあいさつ
思いを語り、次の一歩へ
この札幌市白石区柏町内会に事業所を立ち上げてから、11年を迎えることができました。これもひとえに、地域の皆さまをはじめ、多くの方々に支えていただいたおかげであり、心より厚く御礼申し上げます。
開所以来、メンバー・スタッフとともに仕事を考え、形にしてまいりました。現在は、障害当事者の視点からの「情報発信」、「動画撮影・編集」、「出張講義」を主な活動として取り組んでいます。
今後も障害者メディア事業所として、社会に対して障害者への理解を深め、共感を生み出し、そして変革への一石となることを願いながら、発信という私たちの力を活かして貢献していきたいと考えております。
近年は、感染症の流行や労働環境の変化などにより、身近な生活の中でも柔軟な対応を求められる場面が増えていると感じます。
そうした中で、メンバーと共に現状に立ち向かい、新たなチャンスを見出していくためにも、ここプロが大切にしてきた「個々のメンバーが思いを語り、互いに思いをやり取りすること」を今後も続けていきたいと考えています。
また、メンバーが思いを語ることが、ご自身の可能性を広げることにつながると信じて、一層の研鑽を重ねてまいります。
引き続き、ここリカ・プロダクションの活動に変わらぬご理解とご協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。
ここリカ・プロダクション
管理者・サービス管理責任者 服部 篤隆
(精神保健福祉士)